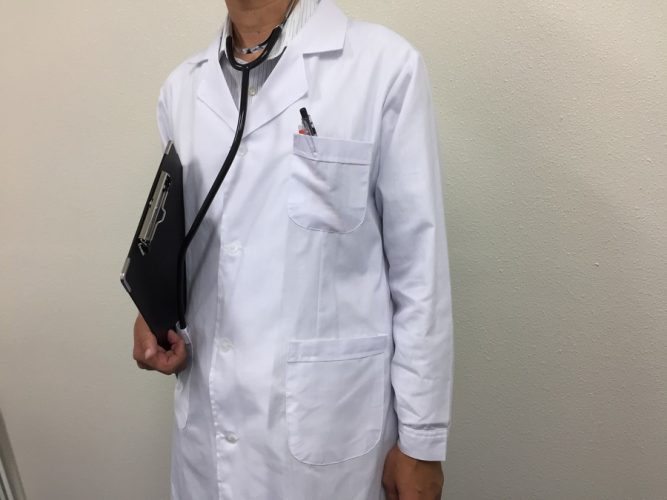医療現場で活躍する医療ソーシャルワーカー
ソーシャルワーカーは様々な場所で活躍している仕事です。
その中でも病院をはじめとした医療機関で働いているソーシャルワーカーは医療ソーシャルワーカーといわれています。
病院へ入院をしたり外来通院していたりする人は体長だけでなく様々なことに常に不安を抱えているものです。
自分の病気が良くなるのか、入院費はどのくらいかかるのか、退院をしてからは今まで通りの生活ができるのか、など不安なことはたくさん出てきます。
こういった疑問に対して患者さんはもちろんその家族に対してもたくさんの不安を聞いて問題解決をしていくために働くのが医療ソーシャルワーカーの仕事です。
具体的な役割としては療養中の相談業務を行うのはもちろんですが退院後の生活支援をしたり社会復帰の援助、経済的な問題の解決、地域活動といったものもあります。
こういった疑問は誰に相談すればよいかわからない人も多くいますし、医師に相談しにくいと思っている人も多いです。
そのため医療ソーシャルワーカーが入院中から退院してからも包括的期に相談に乗って必要に応じて解決策を図っていきます。
医療ソーシャルワーカーはどこで働いているのか
医療ソーシャルワーカーは名前から病院で働いていると思われがちですが、病院だけでなく介護老人保健施設や精神障害者社会復帰施設など保健医療機関でも多く活躍している仕事です。
一般的なソーシャルワーカーと同じく特に資格がなくても働くことができます。
しかし取り扱う内容は多岐にわたりますし専門的な知識も必要です。
そのため社会福祉士や社会福祉主事資格が求められる場合もあります。
医療ソーシャルワーカーに生かせる資格やスキル
医療ソーシャルワーカーになるために必須の資格はないですが、社会福祉士や精神保健福祉士の資格があると仕事も進めやすいですし優遇されるケースも多いです。
無資格未経験からも始められますが、福祉のことや医療のことなど覚えるべきことも多くありますから仕事を始めてから勉強が必要となることも多くあります。
そのためすぐに医療ソーシャルワーカーとして働くのではなく、医療機関や福祉機関で実務経験を積んだうえで仕事を始めることが望ましいです。
また、医療ソーシャルワーカーとして働く際には資格だけでなくコミュニケーション能力やプランニング力といったものも必要です。
ソーシャルワーカーの対象となる人とその家族はもちろんですし、関連機関との連携をとることも大切になってきます。
そのため医療や福祉の知識だけでなく仕事を円滑に進めるためにコミュニケーション能力や社会性、リーダーシップのとり方といったことについても勉強しておくことが必要です。